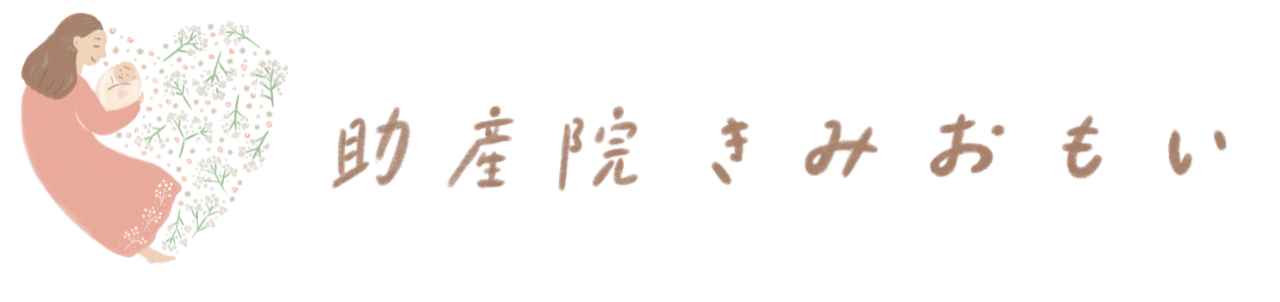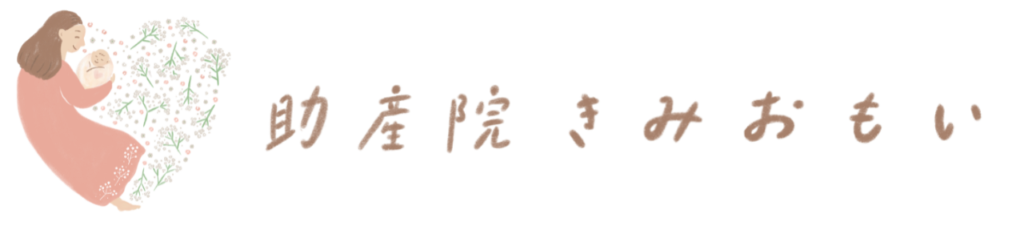赤ちゃんを迎えた喜びとともに、心や体の変化に戸惑うママは少なくありません。
特に「産後うつかもしれない…」と不安を抱える方は多いのではないでしょうか。
 助産師きみ
助産師きみ産後うつの症状や、いつからいつまで続くのか、乗り換え方まで助産師がまとめたので参考にしてください。
産後うつとは?

産後うつは、出産後にホルモンバランスの変化や環境の変化が影響し、気分の落ち込みや不安が強くなる状態です。
単なる疲れや気分の波と違い、長期間にわたり続くことが特徴です。
産後うつの症状

産後うつの症状は人それぞれですが、主に以下のようなものがあります。
産後うつの症状例
- 気分の落ち込み → 何をしても楽しくない、涙が止まらない
- 不安や焦り → 赤ちゃんのお世話がうまくできていない気がする
- イライラしやすい → 夫や家族に対して怒りっぽくなる
- 食欲の変化 → 食欲がなくなる、または過食してしまう
- 眠れない → 赤ちゃんが寝ていても眠れない、逆に過眠する
- 極端な自責の念 → 「私は母親失格だ」と思い込む
症状が軽いうちは「産後ブルー」とも呼ばれ、比較的短期間で改善することもあります。
 助産師きみ
助産師きみしかし長引く場合は産後うつの可能性があるため、早めの対策が大切です。
産後うつはいつから始まる?

産後うつは、一般的に出産後2週間〜3ヶ月の間に発症することが多いとされています。
出産直後はホルモンの急激な変化によって気分が落ち込むことがあり、これが産後ブルー(マタニティ・ブルーズ)と呼ばれます。
産後ブルーは理由もなく泣けてきたり、育児への不安や責任感を感じてイライラしたり、涙もろくなったり気分が変わりやすくなったりします。
 助産師きみ
助産師きみ助産師の私でさえも産後2日目にわけもなく泣けてきて病室で泣いた覚えがあります。

程度に違いはありますが、ホルモンの急激な変化が関係していると言われていて誰にでも起こりうることです。
ただし産後ブルーは一時的なもので、多くの場合2週間以内に改善します。
そして産後ブルーが長引いて重症化すると産後うつになることも。
 助産師きみ
助産師きみ産後ブルーの不安が強いときや、症状がいつまでも続く場合は早めに助産師などに相談することをおすすめします。

一方で、産後うつは産後1ヶ月〜3ヶ月頃に本格的に始まることが多く、放置すると半年〜1年以上続くことも。
なかには産後1年以上経過してから発症するケースもあります。
産後うつはいつまで続く?

産後うつの期間は個人差がありますが、一般的には数ヶ月から1年程度続くことが多いです。
早めに適切なケアを受ければ回復が早くなりますが、放置すると長引き、慢性的なうつ状態に移行する可能性も。
 助産師きみ
助産師きみ心の不調が続く場合は、無理をせず専門家に相談することが大切です。
産後うつになりやすい人の特徴

産後うつは誰にでも起こりうるものですが、特になりやすい傾向のある方がこちら。
- もともと不安を感じやすい性格
- 完璧主義で育児に強いプレッシャーを感じる
- 妊娠中や過去にうつの既往歴がある
- 家族やパートナーのサポートが少ない
- 育児に対する不安が強い
- 体調の回復が遅れている(産後の体力低下や睡眠不足)
こうした要因が重なると、産後うつのリスクが高まりやすいです。

特に今ではネットでさまざまな情報が手に入るため「これをやらなきゃ」「やった方がいいかな…」と思いつつも、計画通りに物事が進まないことに戸惑いやストレスを感じるかもしれません。
でも赤ちゃんのお世話は思い通りにいかないのが当たり前。
 助産師きみ
助産師きみ育児は「100点満点を目指すもの」ではなく「60点で十分」くらいの気持ちで向き合うのがちょうどいいんです。赤ちゃんにとってもママが笑顔でいることが一番大切なので。

たとえば下記のような気持ちに余裕をもつのが大切。
- 部屋が少し散らかっていてもOK
- 毎日手作りごはんじゃなくてもOK
- 赤ちゃんが泣き止まなくても「今できることはやった!」と思ってOK
 助産師きみ
助産師きみ「今の自分で大丈夫」と、自分に優しくしてあげてくださいね。
産後うつの対策と乗り越え方

産後うつの症状を和らげるために、以下の対策を意識しましょう。
- 周囲のサポートを積極的に受ける
- 睡眠を確保する
- 産後ケア施設や専門家に相談する
- ひとりの時間を作る
- 食事と運動で体調を整える
周囲のサポートを積極的に受ける

「自分がやらなければ」と無理をしすぎると、心身ともに疲弊してしまいます。
家族やパートナーに頼れることは積極的にお願いしましょう。
 助産師きみ
助産師きみ自治体の産後ケアサービスを利用するのもおすすめですよ。
睡眠を確保する

睡眠不足は心のバランスを崩しやすくします。
赤ちゃんのお世話を交代してもらったり、昼寝を取り入れるなどして、少しでも休息を取るよう心がけましょう。
産後ケア施設や専門家に相談する
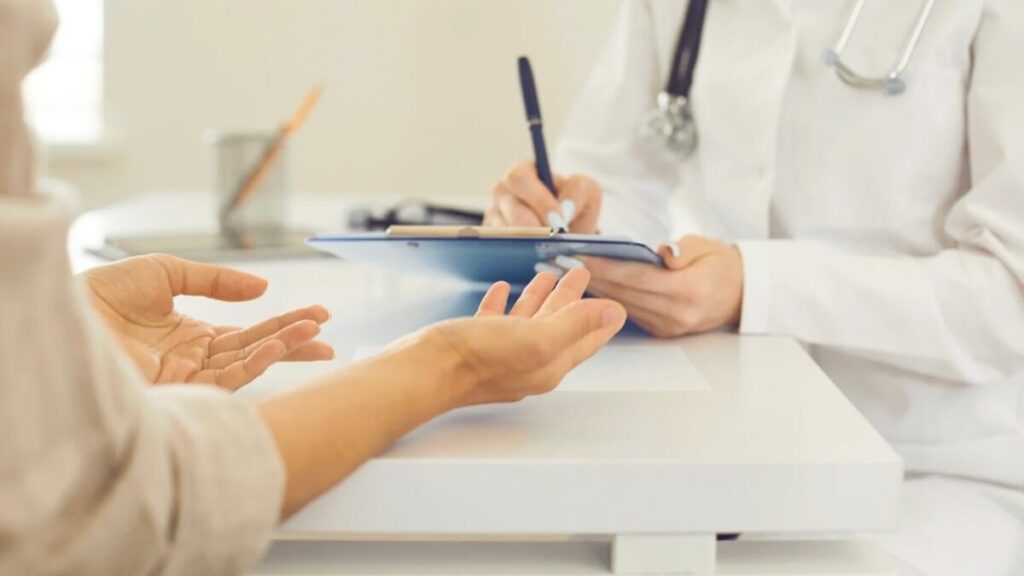
助産師やカウンセラーなど、専門家のサポートを受けることも大切です。
産後ケア施設を利用したり、オンライン相談を活用するのも良い方法です。
ひとりの時間を作る

赤ちゃんと24時間向き合い続けると、精神的な負担が大きくなります。
短時間でもいいので、一人の時間を確保し、リフレッシュする時間を持ちましょう。
しかし産後は赤ちゃんのお世話に追われ「そもそも一人になれる時間なんて取れない…」と自分の時間を持てないと悩む女性も多いのではないでしょうか。
そんなときは、「短時間でもOK」と考え方を変えることが大切。
 助産師きみ
助産師きみたとえば、赤ちゃんが昼寝をしている間の5分間でも、一息ついて温かいお茶を飲む、好きな音楽を聴く、深呼吸をするなど、自分のための時間を意識的に作ってみましょう。

またパートナーや家族、行政のサポートを活用することも大切です。
「ちょっとの時間だけでも見ていてほしい」と具体的に頼むと、意外と協力してもらいやすいことも。
家事や育児をすべて自分で抱え込まず「お願いできることはお願いする」ことで、ひとりになれる時間を生み出しやすくなります。
食事と運動で体調を整える

バランスの取れた食事と適度な運動は、心の健康にも良い影響を与えます。
無理のない範囲で、栄養のある食事やストレッチなどを取り入れましょう。
さいごに。助産師から伝えたいこと

産後うつは、決して「気の持ちよう」や「頑張りが足りない」ものではありません。
ホルモンバランスの急激な変化、睡眠不足、環境の変化などが重なり、心と体に大きな負担がかかることで起こります。
 助産師きみ
助産師きみ誰にでも起こりうることだからこそ、「私だけが弱いわけじゃない」と知ってほしいのです。

そして、産後うつを防ぐためにはママが一人で頑張りすぎないことがとても大切。
そのためには、周囲の協力が欠かせません。
特に夫のサポートはママの心の負担を大きく減らす鍵になります。
 助産師きみ
助産師きみできればこの記事は旦那さんに読んでほしい記事でもあります。赤ちゃんが生まれると、ママは一日中お世話に追われ、心も体も限界に近いことがあるので「何か手伝うことある?」ではなく、「俺が〇〇するね」と具体的に動くことでママの負担はぐっと減らせるはず!

育児は夫婦二人で乗り越えるもので「二人の子どもを一緒に育てている」という気持ちを持つことが、ママにとって何よりの安心感に繋がります。
 助産師きみ
助産師きみパートナーと支え合い、周囲の助けも借りながら、無理をせずに乗り越えていきましょう。