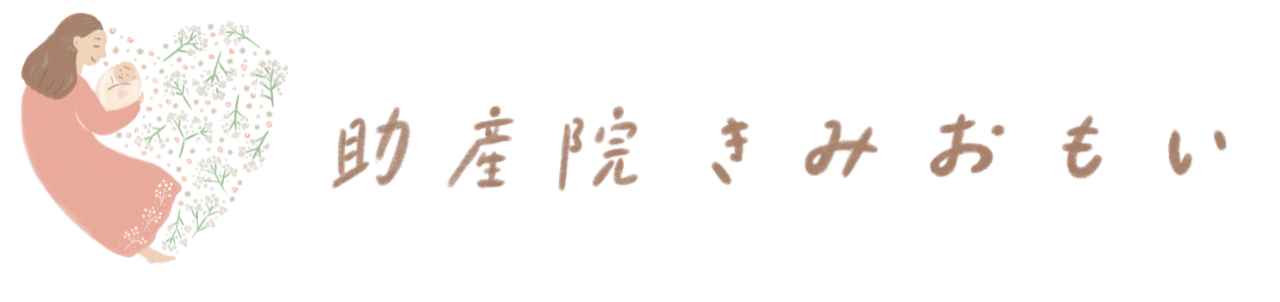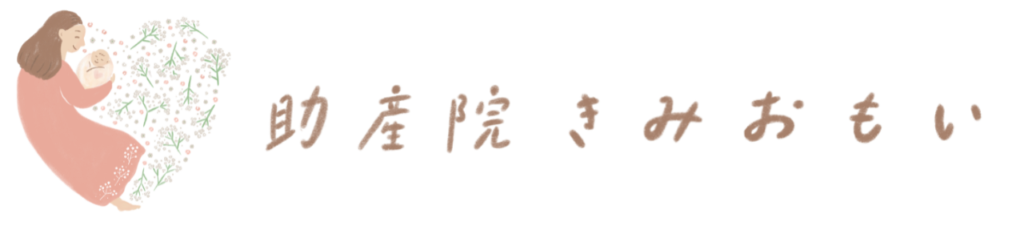妊娠後期の健診で「B群溶連菌(GBS)陽性です」と言われ、不安な気持ちになった方もいるかもしれません。
初めて聞く名前に戸惑い「私が感染してるってこと?」「赤ちゃんにうつる?」「どうしたらいいの?」と心配が広がりますよね。
 助産師きみ
助産師きみこの記事では、妊婦さんが安心して出産にのぞめるように、GBSの基本知識から検査の流れ、赤ちゃんへの影響、そして2人目妊娠のときの注意点まで、助産師の視点でやさしく解説していきます。
B群溶連菌(GBS)ってなに?妊婦さんが気をつけたい理由

GBS(Group B Streptococcus)とは、主に腸や膣にすんでいる常在菌の一種。
健康な成人の20〜30%に見られ、ふだんはとくに悪さをしません。
でも妊婦さんの場合、出産時に赤ちゃんに感染することがあり、生まれてすぐに体調を崩すリスクがあるため注意が必要です。
 助産師きみ
助産師きみつまり、GBS=怖い感染症というよりも、「事前に見つけておけば防げる可能性が高い」ものなのです。
どこから感染するの?GBSの感染経路とリスク

妊婦さん自身に症状が出ることは少なく、感染していても自覚がないことがほとんどです。
ですが、分娩時に膣内のGBSが赤ちゃんに触れることで、まれに「新生児GBS感染症」を引き起こすことも。
 助産師きみ
助産師きみとくに陣痛が始まってから時間がたつ・破水してから時間がたつなどの条件が重なると、感染リスクが高まるとされています。
胎内感染は非常にまれですが、生まれてすぐに感染してしまうケースには注意が必要です。
検査はいつ?痛くない?GBSスクリーニングの時期と方法

GBSの検査は、妊娠35〜37週ごろの妊婦健診のタイミングで行われます。
検査方法はシンプルで、膣と肛門周囲を綿棒で軽くぬぐうだけ。
 助産師きみ
助産師きみ少しヒヤッとすることもありますが、痛みはほとんどありません。

検査結果は数日後〜1週間ほどで出ます。(陽性だった場合には、出産時に点滴で抗生剤を使って予防を行います)
検査費用については、病院によって異なりますが、保険適用外のケースが多く、1,000〜3,000円程度が目安です。
GBS陽性だったらどうなるの?出産時の対応

GBS陽性とわかった場合、多くの病院では「分娩中に抗生剤の点滴をする」ことで赤ちゃんへの感染を防ぎます。
この抗生剤は主にペニシリン系。陣痛が始まってから静脈に点滴で投与され、数時間ごとに繰り返されることが多いです。
重要なのは、「陽性=帝王切開」ではないということ。
 助産師きみ
助産師きみ基本的には自然分娩が可能であり、感染予防をしっかり行えば、お産そのものに大きな影響はありません。
赤ちゃんへの影響は?GBS感染で起こる症状とその予防

新生児GBS感染症には、大きく分けて「早発型」と「遅発型」があります。
とくに問題となるのは、出産後24時間以内に発症する早発型。
主な症状例
- 呼吸困難
- 敗血症
- 肺炎
- 髄膜炎(まれ)
 助産師きみ
助産師きみ発症率は0.2〜0.4%とされており、非常にまれなものですが、重症化することがあるため注意が必要です。
ただし分娩中に適切に抗生剤を投与すれば、そのリスクは大幅に減らすことができます。
実際に抗生剤予防を行うことで、感染率は10分の1以下になるとも言われています!
2人目の妊娠ではどうなるの?再び陽性になることもある?

1人目のときにGBS陽性だった方は、「2人目もまたなるのかな?」と不安になるかもしれませんね。
実は、GBSは体の中で増減をくり返す菌。
 助産師きみ
助産師きみ1回目は陽性でも、次の妊娠で陰性になるケースもありますし、その逆もあります。
そのため、毎回の妊娠ごとに再検査が必要です。
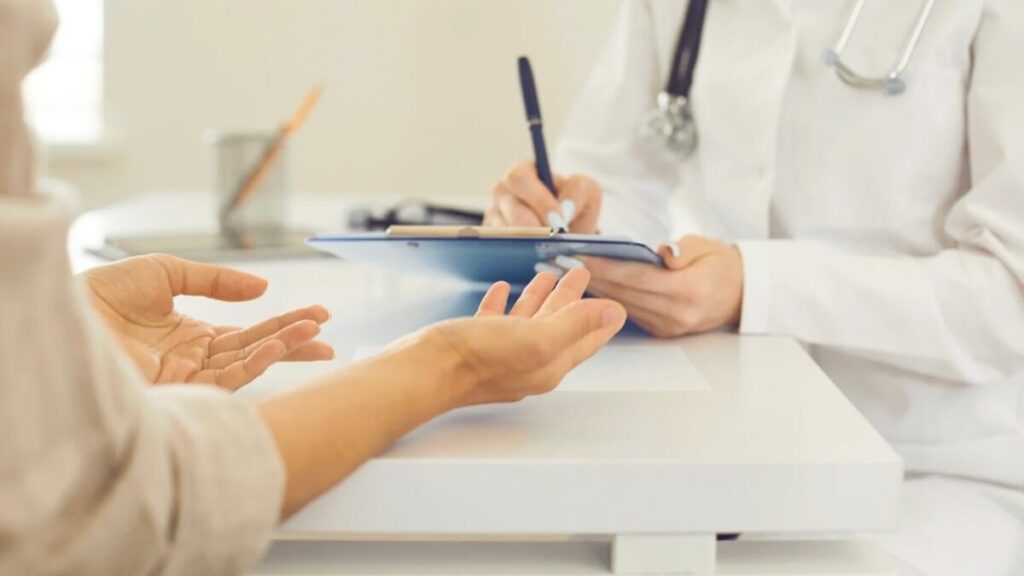
また、過去にGBS陽性だった場合や、赤ちゃんがGBS感染症になったことがある場合は、検査で陰性でも抗生剤を使うこともあり。
 助産師きみ
助産師きみ2人目のときも、早めに健診で相談しておくと安心ですね。
助産師から伝えたいこと

GBS陽性と聞いて驚く方が多いですが、実は「誰でも持っている可能性のある常在菌」で決して特別なことではありません。
大切なのは、検査で事前に把握して、必要な処置を受けること。
B群溶連菌(GBS)は、妊婦さんや赤ちゃんにとって注意が必要な存在ではありますが、正しく知り、備えることで怖いものではなくなります。

陽性と言われてもしっかり対応すれば赤ちゃんへの影響はほとんどなく、安全に出産を迎えられることが多いです。
2人目以降の妊娠でもあせらず、毎回の健診を大切にしていきましょう。
 助産師きみ
助産師きみ赤ちゃんを守るために、不安なことがあればひとりで抱えこまないこと。何か心配な点があれば、助産師や医師になんでも相談してくださね。